「伊達に試合を重ねていない。“引き出し”は作ってきた」

コーチングで周囲を動かすのもボランチの仕事。試合の状況に応じて自身のプレーを変えつつ、「声で周りを動かせるボランチがいるのは、攻守において重要」だ。写真:茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)
――常に微調整しているんですね。
「よく“自分たちのスタイル”って言いますけど、それがハマらなかったり、相手のほうが上手く行っている時間帯は必ずある。そこで微調整して変化を付けられるのは、アントラーズの強みでもあると思います。まずは自分たちのスタイルで押し切ろうとするけど、それが上手く行かない時でも対応する術を持っているチームです」
――状況に対応する術は練習で身に付くものでしょうか?
「感覚的なものが大きいかな。あとはやっぱり、自分としては伊達に試合数を重ねていないんで。リーグ、天皇杯、ナビスコカップ、五輪代表や日本代表。満員の国立で勝てば優勝、負ければなにも残らないといったタイトルが懸かった状況……。いろんなケース、シチュエーションで、何試合やらせてもらったか分からない。どうすれば勝てるという絶対的なものはないけど、そのなかで『こうやれば上手く行くんじゃないかな』という“引き出し”は作ってきたし、そこは俺らがやるべき仕事だと思っています」
――その引き出し作りは、チームの中心である小笠原選手というキャラクターだけでなく、ボランチというポジションに求められる役割でもあると思います。
「そういう“サッカーを知っている選手”がボランチにいるのは、チームにとって大きい。強いチームには、中心にどっしりと構える選手がいます。例えば、0-1から失点して0-2になった時には、1点差の戦い方はできないわけで。だからと言って、いちいち監督に指示を仰ぐ暇はない。そこは自分たちで対応すべきです。試合の状況が変われば、プレーも変化させなければいけない。それを自分でできて、声で周りを動かせるボランチがいるのは、攻守において重要です」
――以前の小笠原選手は、攻撃的なポジションで活躍していました。今のスタイルへのターニングポイントとなったのは、やはりセリエA挑戦でしょうか?
「そうですね。俺が06年から約1年プレーしたメッシーナは、最終的には2部に落ちたように“勝てないチーム”でした。だから当然、自分たちがボールを持てる時間は少なかった。セカンドボールを拾ったり、カウンターを潰したりして、そこからサッカーが始まりましたから。そのなかで中盤に求められたのは、まずは守備をしてボールを奪う仕事。生き残るためには守備をするしかなかったし、そこで守備のほとんどを学んだと思います」
――まさにボランチに近付いていった感じですね。
「自分に足りなかったものを勉強させてもらいました。それまではとにかく点に絡みたかったし、ゴール前で仕事がしたかった。でも、当時はまったく逆の部分を求められていたので。イタリアの選手は相手を潰すのが上手いから、学ぶところは多かったですね」
――攻撃的MFにはない、ボランチの楽しみを見つけた?
「それはあります。相手からボールを奪う感覚っていうか。向こうのチャンスの時、ボールを追うだけでズルズル下がるのと、食い止めてこっちの攻撃につなげられるのとでは、本当に大きな差が出る。自分たちのピンチを、一気にチャンスへと変えるようなプレー。そこに快感を覚えるようになりました」
「よく“自分たちのスタイル”って言いますけど、それがハマらなかったり、相手のほうが上手く行っている時間帯は必ずある。そこで微調整して変化を付けられるのは、アントラーズの強みでもあると思います。まずは自分たちのスタイルで押し切ろうとするけど、それが上手く行かない時でも対応する術を持っているチームです」
――状況に対応する術は練習で身に付くものでしょうか?
「感覚的なものが大きいかな。あとはやっぱり、自分としては伊達に試合数を重ねていないんで。リーグ、天皇杯、ナビスコカップ、五輪代表や日本代表。満員の国立で勝てば優勝、負ければなにも残らないといったタイトルが懸かった状況……。いろんなケース、シチュエーションで、何試合やらせてもらったか分からない。どうすれば勝てるという絶対的なものはないけど、そのなかで『こうやれば上手く行くんじゃないかな』という“引き出し”は作ってきたし、そこは俺らがやるべき仕事だと思っています」
――その引き出し作りは、チームの中心である小笠原選手というキャラクターだけでなく、ボランチというポジションに求められる役割でもあると思います。
「そういう“サッカーを知っている選手”がボランチにいるのは、チームにとって大きい。強いチームには、中心にどっしりと構える選手がいます。例えば、0-1から失点して0-2になった時には、1点差の戦い方はできないわけで。だからと言って、いちいち監督に指示を仰ぐ暇はない。そこは自分たちで対応すべきです。試合の状況が変われば、プレーも変化させなければいけない。それを自分でできて、声で周りを動かせるボランチがいるのは、攻守において重要です」
――以前の小笠原選手は、攻撃的なポジションで活躍していました。今のスタイルへのターニングポイントとなったのは、やはりセリエA挑戦でしょうか?
「そうですね。俺が06年から約1年プレーしたメッシーナは、最終的には2部に落ちたように“勝てないチーム”でした。だから当然、自分たちがボールを持てる時間は少なかった。セカンドボールを拾ったり、カウンターを潰したりして、そこからサッカーが始まりましたから。そのなかで中盤に求められたのは、まずは守備をしてボールを奪う仕事。生き残るためには守備をするしかなかったし、そこで守備のほとんどを学んだと思います」
――まさにボランチに近付いていった感じですね。
「自分に足りなかったものを勉強させてもらいました。それまではとにかく点に絡みたかったし、ゴール前で仕事がしたかった。でも、当時はまったく逆の部分を求められていたので。イタリアの選手は相手を潰すのが上手いから、学ぶところは多かったですね」
――攻撃的MFにはない、ボランチの楽しみを見つけた?
「それはあります。相手からボールを奪う感覚っていうか。向こうのチャンスの時、ボールを追うだけでズルズル下がるのと、食い止めてこっちの攻撃につなげられるのとでは、本当に大きな差が出る。自分たちのピンチを、一気にチャンスへと変えるようなプレー。そこに快感を覚えるようになりました」

























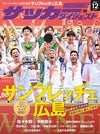 定価:800円(税込)
定価:800円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込)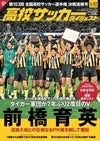 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
