2000シドニー五輪――力を証明した逆転劇

タレント集団といわれたチーム。A代表を兼任するフィリップ・トルシエに率いられた魅力的な集団は、4年前とは異なり、余裕を持って五輪へのチケットを手にした。 (C) SOCCER DIGEST
1999年11月6日@国立競技場(東京)
○3-1 カザフスタン
前半だけでもホームチームのシュート数は2桁に達していた。「かえってラインが上がりすぎていたかもしれない」(中田浩)という日本は、立ち上がりから中田英、中村を起点として、カザフのプレッシングの網をかいくぐりつつ、ヒタヒタとゴール前へと詰め寄っていった。
14分には、中田英のパスを受けて明神が右サイドを突き抜け、福田のダイレクトシュートが生まれる。その数分後には明神がダイレクトボレーを放つ。稲本がドリブルで突っかければ、中田英もミドルを披露する。中村、中田浩のクロスもカザフゴール前へと何度となく降り注いだ。
平瀬には頭へ、福田には足元へと狙いを定めたセンタリングのクロスの精度も、それほどルーズだったわけではない。「細かいミスが多かった」と自嘲するする遠藤を除くと、日本のプレーヤーの動きはほぼ一様に軽快で、前回のタイ戦と比較しても、日本はよほど危険な香りを見せていた。
しかし前回のアウェーゲーム以上に、カザフのDF陣は堅固な壁を築いていた。DFラインでは常にコズーリンが余る。中田英には、劣勢ではありながらもアルチョモフが張り付いているため、周囲はボールを預けにくい。
SBも最終ラインに居座ったままで、さらにはGKロリヤが舌を巻くほどに当たっている。劣勢は承知のうえ。ある意味で、ゲームの流れはカザフの計算通りに進んでいたと言うこともできる。
攻め手は右サイドに絞られており、起死回生の一発に望みを託すしかなかったが、守りに集中することでゲームのリズムを掴んでいったカザフには、そのワンチャンスが巡ってくるのである。
29分、右サイドからのFK。鋭い弧を描いたバルティエフのキックは、シェフチェンコの頭を経由してネットを揺らした。ゾーン気味に守る日本選手の視野を背番号10が横切った時には、すでに手遅れだった。
カザフにとって不幸だったのは、先制ゴールを奪った後も日本が我を忘れることなく、ますます攻勢を強めてきたことだろう。そして日本にとって幸運だったのは、カザフに追加点を期待できるほどの攻め手がなかったことだった。
中村は「(日本は)あの1点だけじゃ逃げ切れないぞっていう攻めができていた」と振り返っていたが、それは他の選手が抱いた感触を代弁するものでもあっただろう。試合後、「このまま攻め続ければ――」と考えていた選手は、ひとりやふたりではない。
後半に入り、日本は本山を左サイドに投入して中村をセンターへ、中田英を前線へと移した。攻撃を意識したこのポジションチェンジによって、ハーフコートマッチの様相はさらに色濃くなった。
前線に入った中田英にMFアルチョモフがそのままマークについたため、かえってカザフゴール前は混雑したが、67分に高原が投入されると一気に背番号28(中田英)へのマークは緩んだ。
そして70分、中田英のセンタリングに平瀬がピンポイントで頭に合わせ、待望の同点ゴールは生まれた。
同点ゴールの余勢を駆った日本は、もはや虫の息になっていたカザフを尻目に、その後も攻撃の手を緩めようとはしない。終盤には今予選の殊勲者である平瀬がポジション定着をアピールする2点目を決め、さらに今予選を通して逞しさを増した中村がトドメのFKを突き刺してみせた。
そしてタイムアップ――。
どこか控えめに、しかしこぼれる笑みを隠すことなく、歓喜を噛みしめる選手とスタッフ。まだ通過点でしかない。だが、いま歩んでいる道は着実に未来へと続いている。日本コールの渦巻く国立で、男たちはそのことを強く印象付けてみせた。
(週刊サッカーダイジェスト1999年11月24日号)
○3-1 カザフスタン
前半だけでもホームチームのシュート数は2桁に達していた。「かえってラインが上がりすぎていたかもしれない」(中田浩)という日本は、立ち上がりから中田英、中村を起点として、カザフのプレッシングの網をかいくぐりつつ、ヒタヒタとゴール前へと詰め寄っていった。
14分には、中田英のパスを受けて明神が右サイドを突き抜け、福田のダイレクトシュートが生まれる。その数分後には明神がダイレクトボレーを放つ。稲本がドリブルで突っかければ、中田英もミドルを披露する。中村、中田浩のクロスもカザフゴール前へと何度となく降り注いだ。
平瀬には頭へ、福田には足元へと狙いを定めたセンタリングのクロスの精度も、それほどルーズだったわけではない。「細かいミスが多かった」と自嘲するする遠藤を除くと、日本のプレーヤーの動きはほぼ一様に軽快で、前回のタイ戦と比較しても、日本はよほど危険な香りを見せていた。
しかし前回のアウェーゲーム以上に、カザフのDF陣は堅固な壁を築いていた。DFラインでは常にコズーリンが余る。中田英には、劣勢ではありながらもアルチョモフが張り付いているため、周囲はボールを預けにくい。
SBも最終ラインに居座ったままで、さらにはGKロリヤが舌を巻くほどに当たっている。劣勢は承知のうえ。ある意味で、ゲームの流れはカザフの計算通りに進んでいたと言うこともできる。
攻め手は右サイドに絞られており、起死回生の一発に望みを託すしかなかったが、守りに集中することでゲームのリズムを掴んでいったカザフには、そのワンチャンスが巡ってくるのである。
29分、右サイドからのFK。鋭い弧を描いたバルティエフのキックは、シェフチェンコの頭を経由してネットを揺らした。ゾーン気味に守る日本選手の視野を背番号10が横切った時には、すでに手遅れだった。
カザフにとって不幸だったのは、先制ゴールを奪った後も日本が我を忘れることなく、ますます攻勢を強めてきたことだろう。そして日本にとって幸運だったのは、カザフに追加点を期待できるほどの攻め手がなかったことだった。
中村は「(日本は)あの1点だけじゃ逃げ切れないぞっていう攻めができていた」と振り返っていたが、それは他の選手が抱いた感触を代弁するものでもあっただろう。試合後、「このまま攻め続ければ――」と考えていた選手は、ひとりやふたりではない。
後半に入り、日本は本山を左サイドに投入して中村をセンターへ、中田英を前線へと移した。攻撃を意識したこのポジションチェンジによって、ハーフコートマッチの様相はさらに色濃くなった。
前線に入った中田英にMFアルチョモフがそのままマークについたため、かえってカザフゴール前は混雑したが、67分に高原が投入されると一気に背番号28(中田英)へのマークは緩んだ。
そして70分、中田英のセンタリングに平瀬がピンポイントで頭に合わせ、待望の同点ゴールは生まれた。
同点ゴールの余勢を駆った日本は、もはや虫の息になっていたカザフを尻目に、その後も攻撃の手を緩めようとはしない。終盤には今予選の殊勲者である平瀬がポジション定着をアピールする2点目を決め、さらに今予選を通して逞しさを増した中村がトドメのFKを突き刺してみせた。
そしてタイムアップ――。
どこか控えめに、しかしこぼれる笑みを隠すことなく、歓喜を噛みしめる選手とスタッフ。まだ通過点でしかない。だが、いま歩んでいる道は着実に未来へと続いている。日本コールの渦巻く国立で、男たちはそのことを強く印象付けてみせた。
(週刊サッカーダイジェスト1999年11月24日号)



























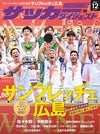 定価:800円(税込)
定価:800円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
