綺麗な崩しの形にこだわりすぎて一本調子な攻撃に。

経験の浅い選手たちをテストしたとはいえ、長谷部ら主軸クラスもピッチに立っていた。シリア戦同様、流れを変えられないまま45分間を過ごしてしまったのはいただけない。写真:滝川敏之(サッカーダイジェスト写真部)
最大の問題点は、やはりビルドアップの精度。相手の守備の狙いを外すような攻撃のバリエーションを持てなかったことだ。前半の日本は短調なロングボールを放り込むしか選択肢がなく、そのパスも前線の動き出しが噛み合わなかったためにまったくチャンスを作れなかった。ベンチで戦況を見守っていた岡崎も、そうしたアイデア不足を感じていたひとりだ。
「一番難しいのは前半だと思う。どんな試合でも前半は相手がモチベーションも高いだろうし、引いてブロックを作って守ってくる相手もいるなかで、自分たちのバリエーションがあんまりないのが一番の課題かなと。そういう部分では、もうちょっと多彩な攻撃が必要になってくると思うし、ハメられている時に抜け出す手段が必要なのかなと感じました」
局面で激しくプレッシャーをかけられてボールホルダーが体勢を崩されれば、それだけ縦パスの精度は落ちる。また、繰り返し裏のスペースを狙うFWの動きに、相手DFが慣れてくるという側面もあるだろう。いずれにせよ、プレッシャーを受けた時の日本の攻撃は一本調子。言い換えれば、プレスから逃げるために縦パスを多用しているだけで、チーム全体としての狙いがハッキリ定まっていない。
これは、シリア戦後に本田が繰り返した「距離感」とも密接に絡んでくる問題だ。イラン戦でも球足の長い縦パスを入れた際の周囲のフォローは遅く、セカンドボールを相手に拾われて攻撃の流れを切る場面は少なくなかった。
ロングボールにも、定石がある。例えば、多少アバウトなボールでも、相手SBの裏のスペースに放り込んで、CFとウイングが連動してプレッシャーをかければ、相手はタッチラインに逃げざるを得なくなる。CBの裏に蹴るボールも同じで、CFがプレス役を務め、トップ下がこぼれ球を回収できるポジションを取れば、少なくともイラン戦のように簡単に縦パスを処理されるような状態にはならない。
シュートパスの崩しにしてもそうだが、日本代表はどうも綺麗な崩しの形にこだわりすぎる傾向がある。それが一本調子な攻撃につながり、一度ハマってしまうとなかなか抜け出せない状況に陥るのだ。
なにも、常に一発で相手の裏を取れるような鮮やかな形を狙う必要はない。岡崎が言う「ハメられている時に抜け出す」には、多少強引にでも相手が嫌がることを徹底する臨機応変さを身もつけるべきではないだろうか。
「一番難しいのは前半だと思う。どんな試合でも前半は相手がモチベーションも高いだろうし、引いてブロックを作って守ってくる相手もいるなかで、自分たちのバリエーションがあんまりないのが一番の課題かなと。そういう部分では、もうちょっと多彩な攻撃が必要になってくると思うし、ハメられている時に抜け出す手段が必要なのかなと感じました」
局面で激しくプレッシャーをかけられてボールホルダーが体勢を崩されれば、それだけ縦パスの精度は落ちる。また、繰り返し裏のスペースを狙うFWの動きに、相手DFが慣れてくるという側面もあるだろう。いずれにせよ、プレッシャーを受けた時の日本の攻撃は一本調子。言い換えれば、プレスから逃げるために縦パスを多用しているだけで、チーム全体としての狙いがハッキリ定まっていない。
これは、シリア戦後に本田が繰り返した「距離感」とも密接に絡んでくる問題だ。イラン戦でも球足の長い縦パスを入れた際の周囲のフォローは遅く、セカンドボールを相手に拾われて攻撃の流れを切る場面は少なくなかった。
ロングボールにも、定石がある。例えば、多少アバウトなボールでも、相手SBの裏のスペースに放り込んで、CFとウイングが連動してプレッシャーをかければ、相手はタッチラインに逃げざるを得なくなる。CBの裏に蹴るボールも同じで、CFがプレス役を務め、トップ下がこぼれ球を回収できるポジションを取れば、少なくともイラン戦のように簡単に縦パスを処理されるような状態にはならない。
シュートパスの崩しにしてもそうだが、日本代表はどうも綺麗な崩しの形にこだわりすぎる傾向がある。それが一本調子な攻撃につながり、一度ハマってしまうとなかなか抜け出せない状況に陥るのだ。
なにも、常に一発で相手の裏を取れるような鮮やかな形を狙う必要はない。岡崎が言う「ハメられている時に抜け出す」には、多少強引にでも相手が嫌がることを徹底する臨機応変さを身もつけるべきではないだろうか。

























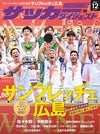 定価:800円(税込)
定価:800円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込)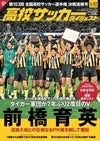 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
