生まれながらの権利を学ぶと、内側からパワーが
一度は完全に離れようとしたスポーツの世界に、井上は戻ってきた。
「今でも冗談で言ったりします。私、スポーツは、あんまり好きじゃないんですよ(笑)って。それでも大きな大会が始まればやっぱり感動しますし、頑張っている人たちは純粋にすごいと思います」
「スポーツ自体が悪いわけではないんです。それを扱う私たちが変わらなければいけない、ということでしょう。課題は多いです。子どもたちを委縮させるプレッシャーではなく、伸ばしていく声掛けが増えれば、コーチも選手も生き生きしながら続けていけるスポーツが増えるのではないか。それを実現している人たちも、実際にいると思います」
JFAを離れた井上は、スポーツを通じた社会課題の解決や国際開発についてさらに学ぶために、筑波大の大学院へと進む。自身の実践経験も踏まえた研究活動を通して可視化できたのが、スポーツならではの価値であり、限界でもあった。
「その日、そのとき、楽しい体験ができたとしても、コミュニティが抱えている根本的な課題自体をスポーツで解決するのは難しい。その限界から目を背けずに取り組みを続けていくのが、実践者のあり方なのだと学びました」
大学院で出会ったのが、セーフガーディングという、井上のライフワークとなる手引きだった。
「社会のいろんな場面で傷つけられている人たちは、セーフガーディングの観点で見ると、決して弱い人たちではありません。権利が守られていないせいで、力を発揮できない・自分で選択できない状況に追いやられている人たちです。私自身はセーフガーディングを、一人ひとりの権利を守ることだと捉えています」
少し噛み砕くとセーフガーディングとは、誰もが等しく持っている基本的な人権を尊重し合うために――実際には多くの場面で尊重し合えていないので――あえて言語化しなければならなかった約束事と言えるだろうか。あきらめる、あきらめない、という話に当てはめるとすれば、井上はきっとこう言うはずだ。
「何かを続ける(あきらめない)選択肢も、あきらめる選択肢も、どちらも自分で自由に選べる権利です。まずは子どもたちが自分で選択できる状況を作り、あきらめる選択肢を選んだら、サポートや支援が必要なのかもしれないと想像する」
私にも選べる権利はある。その気づきは、井上をさらに変化させた。
「人権という、自分の生まれながらに持っている権利を学ぶことで、私自身も自分の内側からものすごくパワーが湧いてきて、溢れるのを感じました」
「今でも冗談で言ったりします。私、スポーツは、あんまり好きじゃないんですよ(笑)って。それでも大きな大会が始まればやっぱり感動しますし、頑張っている人たちは純粋にすごいと思います」
「スポーツ自体が悪いわけではないんです。それを扱う私たちが変わらなければいけない、ということでしょう。課題は多いです。子どもたちを委縮させるプレッシャーではなく、伸ばしていく声掛けが増えれば、コーチも選手も生き生きしながら続けていけるスポーツが増えるのではないか。それを実現している人たちも、実際にいると思います」
JFAを離れた井上は、スポーツを通じた社会課題の解決や国際開発についてさらに学ぶために、筑波大の大学院へと進む。自身の実践経験も踏まえた研究活動を通して可視化できたのが、スポーツならではの価値であり、限界でもあった。
「その日、そのとき、楽しい体験ができたとしても、コミュニティが抱えている根本的な課題自体をスポーツで解決するのは難しい。その限界から目を背けずに取り組みを続けていくのが、実践者のあり方なのだと学びました」
大学院で出会ったのが、セーフガーディングという、井上のライフワークとなる手引きだった。
「社会のいろんな場面で傷つけられている人たちは、セーフガーディングの観点で見ると、決して弱い人たちではありません。権利が守られていないせいで、力を発揮できない・自分で選択できない状況に追いやられている人たちです。私自身はセーフガーディングを、一人ひとりの権利を守ることだと捉えています」
少し噛み砕くとセーフガーディングとは、誰もが等しく持っている基本的な人権を尊重し合うために――実際には多くの場面で尊重し合えていないので――あえて言語化しなければならなかった約束事と言えるだろうか。あきらめる、あきらめない、という話に当てはめるとすれば、井上はきっとこう言うはずだ。
「何かを続ける(あきらめない)選択肢も、あきらめる選択肢も、どちらも自分で自由に選べる権利です。まずは子どもたちが自分で選択できる状況を作り、あきらめる選択肢を選んだら、サポートや支援が必要なのかもしれないと想像する」
私にも選べる権利はある。その気づきは、井上をさらに変化させた。
「人権という、自分の生まれながらに持っている権利を学ぶことで、私自身も自分の内側からものすごくパワーが湧いてきて、溢れるのを感じました」
だから、君にも、あなたにも、権利はあるんだよと、多くの子どもたちに伝えたい。子どもたちが自分の権利を知り、いやだと思うときに「NO」と言えるようになるためのプログラムを作り、広めていくのも井上のひとつの目標だ。
昨年の夏には、指導者向けの試験的な講習会を開催した。将来的には、権利侵害の加害者となった指導者が、やり直すためのプログラムも作りたい。
井上がそう構想する背景に、かつて暴力や暴言等の被害者だった子どもたちが、やがて加害者の大人になっているという“再生産”の構造がある。井上は「この表現はちょっと上から目線なんですが」と断ったうえで、「加害者の更生プログラム」についての話をこう続ける。
「大人になって不適切な指導をしてしまっている人たちのなかには、子どもの頃は自分が不適切な指導の被害者だったというケースがとても多くあります。問題は加害を受けていたときに、ちゃんと被害者になれていなかったことなんです。
被害者になれていないから、加害者になった自分に気づかない。必要なのは、かつての自分は権利を傷つけられていた。本当は心が痛かったと認めることです。そのようなしっかりしたプロセスを経て、現場に復帰できる仕組みを作れたら...」
そう語る井上に、こちらも「失礼な質問かもしれませんが」と断りを入れたうえで、あえて聞く。権利を尊重し合うって、本当はそんなに難しいことではないですよね。権利について学んで、考え方を変えるのは――。
「そうなんです。当たり前に人権教育がなされていたら、子どもたちのNOのためのプログラムも、加害者のための更生プログラムもきっと必要ありません」
◇
ハッピースポーツ教室の井上は、取材中と同じか、それ以上にハキハキ、ニコニコ、そして生き生きしていた。バルサ財団の日本での取り組みは4年間でひとまず幕が引かれたが、そのメソッドや精神は受け継がれているだろう。
井上たちはいろいろ試行錯誤しながら、試合での勝利に最大の価値を置く競技スポーツとはまた別の選択肢を確立しようと試みる。そうした実践の場は、ハッピースポーツ教室以外にも持っている。
ある日の実践中の出来事だ。井上はある子どもの姿に、強く心を動かされていた。
まだ10歳かそこらの、ここではAさんとしておこう。Aさんは感情のコントロールに難しさがあり、それまでの活動では思いどおりに事が運ばない場面で取り乱したり、他の参加者と衝突したりするケースが多かった。
ところがその日のAさんの表情には、どこか誇らしさが見て取れたのだ。普段なら他の子の行動に苛立ち、八つ当たりしていてもおかしくない場面で、Aさんはおそらく自分の心と葛藤しながら、誰もが正しいと口を揃えるような行動に出る。他の子を思いやり助けるという選択肢を、実行に移してみせたのだ。
なぜ、私はあんなに感動していたのだろうか。井上がその理由を言語化できたのは、しばらくしてからだ。どれだけ自分が正しいと思える行ないでも、実行に移すには勇気が必要なときもある。井上は例え話で、人目の多い公共の場で見知らぬ人を手助けするとき、親切だとわかっていても勇気を振り絞るという話をしてくれた。
勇気を出して行動したときに湧いてくる感情は、困っている人を助けた誇らしさではなく、正しい・こうありたいと自分が思うことを実行できた誇らしさではないか。Aさんのあの表情がきっとそれだったと、井上は理解した。
連載50回目というひとつの節目で、井上を取材させてもらったのは、はたして偶然だったのか。取材中、井上は自分のことを「あまのじゃくだ」と形容していた。きっと、あまのじゃくは、マイノリティの別の表現だ。
あまのじゃくだからこそ、井上は現在に至る道を切り拓くことができたのではないか。マイノリティだからこそ、これからも未来を切り拓いていくのではないか。だから、こう思う。いつまでも、マイノリティたちの様々な挑戦や取り組みを、紹介しつづけていきたいと。(文中敬称略)
取材・文●手嶋真彦(スポーツライター)
※サッカーダイジェスト2023年9月号から転載
「言っていることが難しくて...」遠藤保仁コーチのFK練習に選手たちも興味津々! G大阪DF黒川圭介も新たな挑戦へ「決める自信が持てたら蹴ってみたい」
「飛び抜けて凄い」18歳のトレーニングパートナーが驚嘆した日本代表戦士は?「ボールを持った時は触れない」【アジア杯】
昨年の夏には、指導者向けの試験的な講習会を開催した。将来的には、権利侵害の加害者となった指導者が、やり直すためのプログラムも作りたい。
井上がそう構想する背景に、かつて暴力や暴言等の被害者だった子どもたちが、やがて加害者の大人になっているという“再生産”の構造がある。井上は「この表現はちょっと上から目線なんですが」と断ったうえで、「加害者の更生プログラム」についての話をこう続ける。
「大人になって不適切な指導をしてしまっている人たちのなかには、子どもの頃は自分が不適切な指導の被害者だったというケースがとても多くあります。問題は加害を受けていたときに、ちゃんと被害者になれていなかったことなんです。
被害者になれていないから、加害者になった自分に気づかない。必要なのは、かつての自分は権利を傷つけられていた。本当は心が痛かったと認めることです。そのようなしっかりしたプロセスを経て、現場に復帰できる仕組みを作れたら...」
そう語る井上に、こちらも「失礼な質問かもしれませんが」と断りを入れたうえで、あえて聞く。権利を尊重し合うって、本当はそんなに難しいことではないですよね。権利について学んで、考え方を変えるのは――。
「そうなんです。当たり前に人権教育がなされていたら、子どもたちのNOのためのプログラムも、加害者のための更生プログラムもきっと必要ありません」
◇
ハッピースポーツ教室の井上は、取材中と同じか、それ以上にハキハキ、ニコニコ、そして生き生きしていた。バルサ財団の日本での取り組みは4年間でひとまず幕が引かれたが、そのメソッドや精神は受け継がれているだろう。
井上たちはいろいろ試行錯誤しながら、試合での勝利に最大の価値を置く競技スポーツとはまた別の選択肢を確立しようと試みる。そうした実践の場は、ハッピースポーツ教室以外にも持っている。
ある日の実践中の出来事だ。井上はある子どもの姿に、強く心を動かされていた。
まだ10歳かそこらの、ここではAさんとしておこう。Aさんは感情のコントロールに難しさがあり、それまでの活動では思いどおりに事が運ばない場面で取り乱したり、他の参加者と衝突したりするケースが多かった。
ところがその日のAさんの表情には、どこか誇らしさが見て取れたのだ。普段なら他の子の行動に苛立ち、八つ当たりしていてもおかしくない場面で、Aさんはおそらく自分の心と葛藤しながら、誰もが正しいと口を揃えるような行動に出る。他の子を思いやり助けるという選択肢を、実行に移してみせたのだ。
なぜ、私はあんなに感動していたのだろうか。井上がその理由を言語化できたのは、しばらくしてからだ。どれだけ自分が正しいと思える行ないでも、実行に移すには勇気が必要なときもある。井上は例え話で、人目の多い公共の場で見知らぬ人を手助けするとき、親切だとわかっていても勇気を振り絞るという話をしてくれた。
勇気を出して行動したときに湧いてくる感情は、困っている人を助けた誇らしさではなく、正しい・こうありたいと自分が思うことを実行できた誇らしさではないか。Aさんのあの表情がきっとそれだったと、井上は理解した。
連載50回目というひとつの節目で、井上を取材させてもらったのは、はたして偶然だったのか。取材中、井上は自分のことを「あまのじゃくだ」と形容していた。きっと、あまのじゃくは、マイノリティの別の表現だ。
あまのじゃくだからこそ、井上は現在に至る道を切り拓くことができたのではないか。マイノリティだからこそ、これからも未来を切り拓いていくのではないか。だから、こう思う。いつまでも、マイノリティたちの様々な挑戦や取り組みを、紹介しつづけていきたいと。(文中敬称略)
取材・文●手嶋真彦(スポーツライター)
※サッカーダイジェスト2023年9月号から転載
「言っていることが難しくて...」遠藤保仁コーチのFK練習に選手たちも興味津々! G大阪DF黒川圭介も新たな挑戦へ「決める自信が持てたら蹴ってみたい」
「飛び抜けて凄い」18歳のトレーニングパートナーが驚嘆した日本代表戦士は?「ボールを持った時は触れない」【アジア杯】















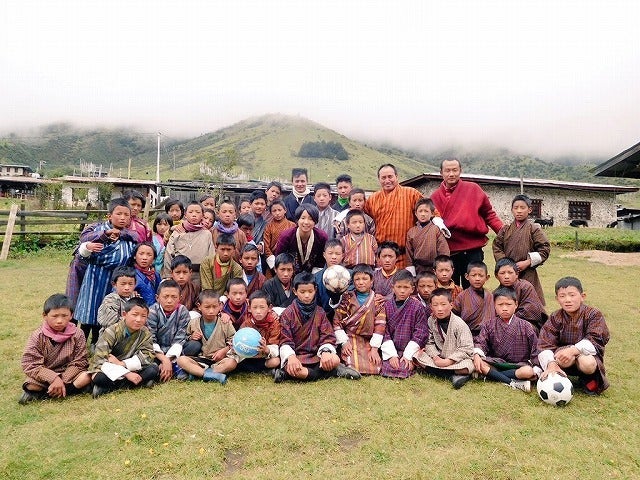










 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
