バルサ化をいとも簡単に放棄するようなことがあれば…
この日、昨季王者の川崎に思い知らされたのは、気が遠くなるようなチームとしての完成度の差だった。中村憲剛、家長昭博、阿部浩之、奈良竜樹、守田英正ら主力をごっそり怪我で欠く川崎は、あえて神戸にボールを握らせ、自慢のパスワークを封印し、奪ってからの縦に速いサッカーでしたたかに勝利を収めている。ただ、主力不在の窮地にこうした“応用編”を平然と繰り出せるのも、パスサッカーという揺るぎない基礎が、迷った時に立ち戻れる原点が、彼らにはあるからだ。そしてそれが、一朝一夕で築き上げられたものでないことは、誰もが知っている。
果たして、神戸というクラブに、長い年月をかけても「日本のバルサになる」という覚悟はあるのだろうか。もしあるのだとしたら、ファン・サポーターも喜んで産みの苦しみをともに味わってくれるだろうし、選手も自分たちのサッカーを信じ、前を向いて戦い続けるに違いない。
古橋は言う。
「全然勝てないなかでも、これだけホームゲームにお客さんが入ってくれる。まだまだリーグ戦は続くし、下を向かずに少しずつでも成長していきたい」
果たして、神戸というクラブに、長い年月をかけても「日本のバルサになる」という覚悟はあるのだろうか。もしあるのだとしたら、ファン・サポーターも喜んで産みの苦しみをともに味わってくれるだろうし、選手も自分たちのサッカーを信じ、前を向いて戦い続けるに違いない。
古橋は言う。
「全然勝てないなかでも、これだけホームゲームにお客さんが入ってくれる。まだまだリーグ戦は続くし、下を向かずに少しずつでも成長していきたい」
けれど、クラブがバルサ化をいとも簡単に放棄し、よもやその目標を「アジアナンバー1クラブ」から「J1残留」に大きく下方修正するようなことがあれば──。
本家バルサも近年の栄華を築く少し前、2000年代初頭にはタイトルから見放される暗黒の時代を過ごしている。当時はカンプ・ノウのスタンドで「クラブから出ていけ」という意味の白いハンカチやタオルが振られるシーンが頻繁に見られたものだが、しかしそれは特定の選手に向けられたものではなかった。サポーターが怒りの矛先を向けるのは、あくまでもチーム作りを主導する会長や監督なのだ。
リーグ戦4連敗が決まった瞬間、ノエビアスタジアム神戸にも珍しくブーイングが響いた。もっとも、その決して大きくはない音量が向かった先には、川崎のファウルを何度となくスルーしたこの日の審判団がいた。一方で、グランドを一周して挨拶をする選手たちには、例によって温かい拍手が降り注ぐ。
そうした愛情に、甘えてはならない。クラブ全体として常に危機感を抱きながら、確固たるスタイルを築き上げていかなくてはならないし、少なくともその意志は毎試合のように示さなくてはならない。だが、仮に神戸が今後も方向性の見えない戦いを続け、意味のない敗戦を重ねるようなら──。さすがに心優しい神戸サポーターも、そっと白いハンカチを懐から取り出すだろう。
取材・文●吉田治良(スポーツライター)













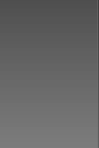
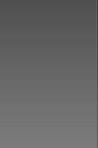











 定価:980円(税込)
定価:980円(税込) 定価:890円(税込)
定価:890円(税込) 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
