チームマネジメントの2つのアプローチ。
とはいえ、筋肉系の故障が最も発生しやすいのは、やはり100パーセントの最大負荷でプレーしなければならない試合の場においてだ。疲労やストレスによるパフォーマンスの低下だけでなく、故障リスクの低減という観点からも、ターンオーバーをはじめとする選手の起用法をどうするかというのは、特に週2試合が日常化しているトップレベルのチームの監督にとっては、きわめて重要なテーマになっている。
これに関しては大きく2つの考え方があるようだ。ひとつは、中2~4日での連戦がもたらすパフォーマンスの低下を避けつつ、グループ全体のモチベーションを高く維持するために、レギュラーと控えという区別を極力廃して、積極的なターンオーバーで選手を回しながらシーズンを戦うというアプローチ。
週2試合ペースで試合に出場している選手は、2試合目までは問題ないが3試合目になるとパフォーマンスが低下する傾向が強く、その原因はフィジカル的な側面よりもむしろストレスなどメンタル的な側面にあるというのは、プロの監督やフィジカルコーチの間で広く言われており、データ的な裏付けもある。
選手の入れ替えによるチームのパフォーマンス低下よりも、個人のパフォーマンス低下や故障リスクの増大の方がトータルでのマイナスは大きいと判断する監督(例えばナポリのラファエル・ベニテス)は、ターンオーバー志向が強い。
もうひとつの考え方は、トレーニングの組み立てやモチベーションコントロールを通じて週2試合のリズムにチームを慣れさせ、それを前提にシーズンを回して行くというアプローチ。
こちらは故障リスクの増大、精神的なバーンアウトや出場機会が少ない選手のモチベーション維持といった問題があるが、それを考慮してもなおチームとしてのパフォーマンスを優先したいという監督(例えばチェルシーのジョゼ・モウリーニョ)たちが採用している。
アプローチは様々だが、インテンシティやパフォーマンスの追求と故障の予防が、トレーニングメソッドからチームマネジメントまで、監督の仕事の多くに関わる最重要テーマになっていることは間違いない。
取材・文:片野道郎
【著者プロフィール】
1995年からイタリア北部のアレッサンドリアに在住し、翻訳家兼ジャーナリストとして精力的に活動中だ。カルチョを文化として捉え、その営みを巡ってのフィールドワークを継続発展させている。『ワールドサッカーダイジェスト』誌や当サイトでも、ロッシ監督とのコラボによる戦術解説や選手分析が好評を博す。62年生まれ、仙台市出身。
これに関しては大きく2つの考え方があるようだ。ひとつは、中2~4日での連戦がもたらすパフォーマンスの低下を避けつつ、グループ全体のモチベーションを高く維持するために、レギュラーと控えという区別を極力廃して、積極的なターンオーバーで選手を回しながらシーズンを戦うというアプローチ。
週2試合ペースで試合に出場している選手は、2試合目までは問題ないが3試合目になるとパフォーマンスが低下する傾向が強く、その原因はフィジカル的な側面よりもむしろストレスなどメンタル的な側面にあるというのは、プロの監督やフィジカルコーチの間で広く言われており、データ的な裏付けもある。
選手の入れ替えによるチームのパフォーマンス低下よりも、個人のパフォーマンス低下や故障リスクの増大の方がトータルでのマイナスは大きいと判断する監督(例えばナポリのラファエル・ベニテス)は、ターンオーバー志向が強い。
もうひとつの考え方は、トレーニングの組み立てやモチベーションコントロールを通じて週2試合のリズムにチームを慣れさせ、それを前提にシーズンを回して行くというアプローチ。
こちらは故障リスクの増大、精神的なバーンアウトや出場機会が少ない選手のモチベーション維持といった問題があるが、それを考慮してもなおチームとしてのパフォーマンスを優先したいという監督(例えばチェルシーのジョゼ・モウリーニョ)たちが採用している。
アプローチは様々だが、インテンシティやパフォーマンスの追求と故障の予防が、トレーニングメソッドからチームマネジメントまで、監督の仕事の多くに関わる最重要テーマになっていることは間違いない。
取材・文:片野道郎
【著者プロフィール】
1995年からイタリア北部のアレッサンドリアに在住し、翻訳家兼ジャーナリストとして精力的に活動中だ。カルチョを文化として捉え、その営みを巡ってのフィールドワークを継続発展させている。『ワールドサッカーダイジェスト』誌や当サイトでも、ロッシ監督とのコラボによる戦術解説や選手分析が好評を博す。62年生まれ、仙台市出身。


























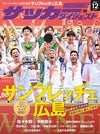 定価:800円(税込)
定価:800円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込)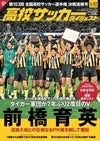 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
