「Jリーグドクターの役割とトレーナーの連携」
池田浩先生は、イビチャ・オシム監督が率いたジェフユナイテッド市原での体験談を披露しました。そのエピソードから、メディカルチームが要求される献身性や、個人ではカバーしきれない部分を助け合うネットワーク作りの大切さといった要素を織り交ぜ、講義を行ないました。

池田 浩(日本サッカー協会 医学委員会委員長)
「サッカー選手の内科的疾患」
土肥美智子先生は、感染症を含めた内科的知識とアンチ・ドーピングについて講義しました。夏季五輪と冬季五輪での内科的疾患の発生率の違いや、ドーピング検査の実施率との相関関係が示された競技記録など、グラフ、データを交えて、わかりやすい解説を行ないました。

土肥美智子(日本サッカー協会 医学委員会委員/アンチ・ドーピング部会長)
●4日目(9月16日)
「育成年代の外傷・障害」
加藤晴康先生は、成長期の障害について、シーバー病(踵の疾患)など、代表的なものをとりあげ、対応策を受講生に考えさせました。また育成年代のケガについては「一時的なもの」「後遺症が残るもの」など、育成年代の選手への対応として、いくつかの判断基準を示しました。

加藤晴康(日本サッカー協会 医学委員会委員)
「サッカー選手の外傷・障害①足関節」
齊藤雅彦先生は、足関節の障害について講義を行ない、「聞く→みる→触る→撮る」という基本サイクルで、特に重要なプロセスとして触るという部分を挙げました。圧痛点を見極め、正しい解剖学の知識、X線検査と照らし合わせることが、正確な診断につながると説きました。

齊藤雅彦(日本サッカー協会 医学委員会委員)
「サッカー選手の外傷・障害②スポーツ救命」
福島理文先生は、サッカーを含むスポーツの現場で、日常的にある脳震盪や熱中症のリスクを紹介しました。また、事故を起こさないための予防策や、発生してしまった際の対応策を、身に沁み込ませておく重要性にも触れました。最後にAEDの操作を含めた救命活動訓練を行ないました。

福島理文(日本サッカー協会 医学委員会 スポーツ救命部会員)
取材・文●西森 彰



























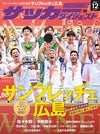 定価:800円(税込)
定価:800円(税込) 定価:980円(税込)
定価:980円(税込)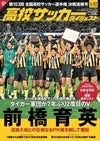 定価:1100円(税込)
定価:1100円(税込)
